笑う犬2010寿
フジテレビの「笑う犬」スペシャル番組のDVD。どのコントも、作り手の熱がこもっているが、特に「出演交渉」での南原清隆による演劇俳優の入れ込みようがすごい。
2枚組で、1枚目は番組完全版、2枚目はオリジナル版だが、この放送されなかったコントが独特の味がある。「10円」の延々と続く人情噺、「ゴールデン通りの人々」のレトロ感覚など、脚本家が好き勝手にやっており、突き抜けた笑いがある。
フジテレビの「笑う犬」スペシャル番組のDVD。どのコントも、作り手の熱がこもっているが、特に「出演交渉」での南原清隆による演劇俳優の入れ込みようがすごい。
2枚組で、1枚目は番組完全版、2枚目はオリジナル版だが、この放送されなかったコントが独特の味がある。「10円」の延々と続く人情噺、「ゴールデン通りの人々」のレトロ感覚など、脚本家が好き勝手にやっており、突き抜けた笑いがある。
内田光子のピアノ、ジェフリー・テイト指揮、イギリス室内管弦楽団によるモーツァルトのピアノ協奏曲第20番、第21番のCDを聴く。しとやかで詩情のあるピアノに、オーケストラが実に相性良く応えている。
NHK大河ドラマ「江」第5回は、「本能寺の変」。江は明智光秀に会ったり、徳川家康の元に現れたりと神出鬼没。おまけに、死に際の織田信長の前に亡霊のように佇む。脚本家のやりたい放題。
戦国時代劇と思うとその軽さについていけない。豪華な俳優陣が演じるSFコメディと割り切ればよいのだろう。
 群馬県総合教育センターで、「ぐんま教育フェスタ」が開催される。長期研修員36名、長期社会体験研修員7名による展示発表を中心に、特別研修員研究成果概要展示や、そば打ち体験、科学の実験・体験などの参加型コーナーなどが設けられた。
群馬県総合教育センターで、「ぐんま教育フェスタ」が開催される。長期研修員36名、長期社会体験研修員7名による展示発表を中心に、特別研修員研究成果概要展示や、そば打ち体験、科学の実験・体験などの参加型コーナーなどが設けられた。
 現在の教育課題に関わる研修員の発表には、多くの来場者が強い関心を持ち、熱心に聞き入り、質問を投げかけていた。この発表そのものが、たいへん実のある研修になっている。
現在の教育課題に関わる研修員の発表には、多くの来場者が強い関心を持ち、熱心に聞き入り、質問を投げかけていた。この発表そのものが、たいへん実のある研修になっている。
午後には、大村はまの愛弟子であり、晩年を支えた苅谷夏子氏による講演「ことばが生きていた教室 -国語教師・大村はまが育てたもの-」が行われた。やさしく語りかけられるその内容は、言語活動の充実の本質に迫るものであった。大村はまが目指した、生きた言葉を使う力を育てることが、今あらためて求められている。
「西から昇った おひさまが 東へ沈む」
赤塚不二夫作品のトリビュートCD。それぞれのアーティストが、思い思いに赤塚不二夫の世界を演奏する。「天才バカボン」のテーマや、ひみつのアッコちゃんのエンディング「すきすきソング」はまだわかるが、「逃げろ!ウナギイヌ!」など、すごい世界になっている。ほとんどハチャメチャのノリ。
乱痴気騒ぎの後、突然、矢野顕子の素敵な曲が流れる。二日酔いの後に回復してくるとき、世の中がとても美しく感じられる、あの気分。
CDの解説に載っている、タモリの話にジンとくる。赤塚が亡くなる一ヶ月ほど前の語りだった。
「これでいいのだ」
という全肯定、フトコロ懐の深さを体現したCD。
赤塚不二夫トリビュート~四十一才の春だから~
オムニバス ロリータ18号 ECD 曽我部恵一 矢野顕子 こおろぎ’73 デブパレード HALCALI ミドリ 電気グルーヴ×スチャダラパー 
「神田川」(かぐや姫) が冒頭の曲となる「続・青春歌年鑑 1973」。「青春時代」は、アリスの歌う曲もあった。「ひなげしの花」(アグネス・チャン) 、「わたしの青い鳥」(桜田淳子)、「ふたりの日曜日」(天地真理) 「中学三年生」(森昌子)など、清楚なアイドルが華やかなりし頃。 優しい曲が多かった。
続・青春歌年鑑 1973
オムニバス 五輪真弓 麻丘めぐみ 郷ひろみ 野口五郎 西城秀樹 桜田淳子 山本リンダ 天地真理 森昌子 千葉紘子 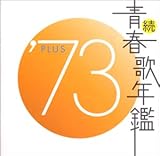
「卒業までの 半年で
答えを出すと 言うけれど」
1977年代、印象に残る多くの曲が生み出された。特に、阿久悠作詞の楽曲は「青春時代」「津軽海峡・冬景色」「宇宙戦艦ヤマト」と多彩を極め、ほとばしる才能に圧倒される。
青春歌年鑑 1977
オムニバス ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 石川さゆり キャンディーズ 郷ひろみ 野口五郎 丸山圭子 森田公一とトップギャラン 清水健太郎 ハイ・ファイ・セット 小柳ルミ子 
「そうだ、やさしいことばでこそ、人の心のなかに入っていけるのだ、むずかしい理論、高い思想、深い感動を、みんなにわかるやさしい、平らな、なめらかなことばで伝えていかなければ、文化はみんなのものにならないのだ」
98歳になるまで、国語教育に渾身で取り組み、多くの生徒たちを育てた大村はま。その教え子であり、晩年はまの仕事を支えた苅谷夏子氏が著した「評伝 大村はま」。
大村はまの人格が形成され、国語教師として実践を重ね、多くの生徒の生涯に影響を与える授業を創り上げる過程を丁寧に描いている。
日露戦争、関東大震災、太平洋戦争、戦後の混乱など、日本の近現代史を背景にしながら、大村はまの関わる人々や当時の学校の様子が生き生きと綴られ、物語としても惹き付けられ、飽くことがない。
はまの学びや実践から、教育に対する様々な考え方が具体的に記され、極めて示唆に富む。
平易な言葉で、するすると読むことができるが、実に多角的な視点で大村はまの人物と実践が語られ、内容はたいへんに深い。心にすんなりと言葉がはいってくる。この本そのものが、大村はまによる国語教育の成果とも言える。
多くの感動と真の敬愛に満ちた、優れた教育書。
なお、著者の苅谷夏子氏による講演会
「ことばが生きていた教室 -国語教師・大村はまが育てたもの-」
が、2011年2月5日、群馬県総合教育センターにおける「ぐんま教育フェスタ」で行われる。
最近のコメント