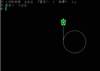 高等学校の先生を対象に、数式処理の講義を行う。まず、日本語版LOGOである「ロゴ坊」を紹介する。
高等学校の先生を対象に、数式処理の講義を行う。まず、日本語版LOGOである「ロゴ坊」を紹介する。
くりかえせ 4 「まえへ 100 みぎへ 90」
で四角が書ける。同様に、三角形など、他の図形を書くことを試みてもらう。そして、円は、どうすれば書けるかを考えてもらう。
くりかえせ 360 「まえへ 1 みぎへ 1」
のような命令で描けることを、こちらから教えるのではなく、子供たちが自分で考えていくことが重要である。自分で描き方が見つかれば、円は正多角形の極限であることが自然と捉えられるであろう。また、タートルは常にその瞬間に向かう方向を示している。円が描けた後で、前に進ませれば、それは接線の方向を表している。つまり、タートルの存在そのものが微分概念を内包しているのだ。このように、LOGOは、数学の概念形成につながることを伝える。
次に、数式処理ソフトの紹介をする。
factor(a^2-b^2)
と命令すると、aの2乗マイナスbの2乗を因数分解し、
(a-b)(a+b)
と出力してくれる。
以前、自分はMathematicaを用いて高校数学を学ぶ本「Mathematicaでトライ! 試して分かる高校数学」を現代数学社から出版し、その内容を高校の授業で実践したことがある。
今回は、教育機関では無料で利用できる数式処理ソフトMuPADを用いて、試行錯誤的に数学を学ぶ課程を、高校の先生方に体験してもらった。自ら数式処理という新しい内容を、テキストに沿って個別に学ぶことで、従来の例題の解法を示し類題を解かせるという形とは違った方法を体験し、それを授業づくりに生かしてもらうことにした。試行錯誤を取り入れた数学の授業の指導案を作成してもらい、1日の講義と演習を終えた。
各人ごとに課題を持ち、探求していけることが、数式処理ソフトのよさだ。
試して分かる高校数学―Mathematicaでトライ!大塚 道明










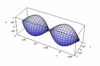


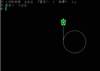

最近のコメント