アニメ もしドラ
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」がNHKでアニメ化され、2011年4月25日より放送される。原作は、累計200万部を越える岩崎夏海の小説。
丁寧な作画がなされ、爽やかな印象。高校生が書籍をひもとき、そこから学んでいくというアニメは、今までありそうでなかった。習得・活用の流れをきちんと具現化しつつ、軽いノリもあって肩肘張らずに見られる。10回のシリーズで、子どもたちと今後も見ていきたいと感じる。
テレビを1時間以上見ないとポイントをためられ、そのポイントを学校で評価するという事業を100万円以上かけてやっている県があるようだが、「テレビを見る」→「親子の会話がなくなる」という考えはあまりに短絡的ではないか。良い番組はたくさんあり、それが元で子どもたちと会話が弾むことも多い。「カンブリア宮殿」は生のキャリア教育となり、「サイエンスZERO」のような理数教育の充実に繋がる番組も多い。教育では「もしドラ」のような作品にも目を向けてよいのでは。
フラッシュ型教材のススメ
フラッシュ・カードのように課題を瞬時に次々と提示するデジタル教材。教室で、毎日繰り返し活用することにより、基礎の定着が図れ、子どもたちの集中力を高めることができる。
シンプルなICT活用のスタイルだが、シンプルゆえに様々な教科で利用できる。達成感が子どもたちの自信につながり、教室が元気になるとの声もある。
先生自らが教材を作り、教室の状況に応じて工夫できる。また、ネット上から教材を手に入れ、手軽に活用することもできる。
基礎・基本の定着や学級経営の活性化に役立つ、フラッシュ型教材の具体例と留意点を満載した有益な書。
フラッシュ型教材のススメ CD-ROM付
高橋純 堀田龍也 
たのしい英文法
英語の基礎的な文法について、語りかけるように丁寧に記した本。英文法を独習しようとする向学心のある学習者にうってつけの本。
英語学習の意義は、論理的に言語を学習する手法を身につけることにもある。コミュニケーションも大事だが、英語を正確に理解するためには文法の学習は欠かせない。その部分が、現行の中学英語の教科書ではややおろそかになっていないか気にかかる。
初版が1975年であるが、今なお多くの人が購入するのは、時代の流れに左右されない価値をこの本が持っているからであろう。
たのしい英文法
林野 滋樹 
人に話したくなる物理
長男が図書館から「人に話したくなる物理」を借りてくる。大学の先生と男女の学生の掛け合いで、物理についての話が語られる。マイクロ波、コリオリの力、物質の状態、偏光などを、電子レンジや携帯電話、3D映像など身近な話題とからめて説明している。
人に話したくなる物理 身近な10話
江馬 一弘 17025研究会 
探査機はやぶさ7年の全軌跡
地球から3億キロメートル彼方の小惑星イトカワまでの往復飛行を成し遂げた探査機はやぶさ。その7年間の軌跡と、投入された数々の技術をビジュアルに解説したニュートン別冊は、まさしく科学のドラマを物語っている。
イオンエンジン、サンプラーホーンなど、前例のない技術を駆使し、世界初の小惑星リターン・ミッションを成功させる。そこには、日本の技術の底力を感じさせる。数々の危機を、周到に準備されたシステムを組み合わせ、あきらめずに工夫を重ねて乗り切る様には感動を覚える。
日本に勇気と希望を与えてくれる貴重なミッションであった。科学技術立国として、世界に誇れる技術を継承し進歩させるためにも、次のプロジェクトの成功を期待したい。
すぐわかる!ビジュアル化学
化学について、図解を駆使して分かりやすく説明した、雑誌ニュートンの別冊「すぐわかる!ビジュアル化学」。原子と周期表、原子の結合、結晶構造などが、工夫されたイラストで表現され、見ているだけでも楽しい。
身近な物質との関わりなども多く記述されている。巻末には、白川英樹、野依良治、田中耕一などノーベル化学賞受賞者のインタビューとその解説も掲載されている。
中学英単語 エイタンザムライDS
ニンテンドーDSの中学生用英単語学習ソフト「中学英単語 エイタンザムライDS」。英語の例文を聴き、空欄の単語を記入していくシンプルなソフト。英語の音声を聴き取りながら書くことで、ヒアリングの力もつく。
中学1年生の長男に買い与えたところ、毎日欠かさずやっている。経験値が上がることで、アイテムが手に入り、キャラクターの着せ替えができる点が気に入っているようだ。また、何日間か続けると、特別なアイテムをゲットできるなど、継続して学習できる工夫もなされている。
はやぶさ帰還カプセル展示 板橋克己展
 はやぶさ帰還カプセルの展示と講演会があるため、群馬県富岡市の自然史博物館、福沢一郎記念美術館に行く。
はやぶさ帰還カプセルの展示と講演会があるため、群馬県富岡市の自然史博物館、福沢一郎記念美術館に行く。
東北大震災から一週間後であり、ガソリンが不足気味のせいか、それほど混んでいなかった。福沢一郎記念美術館では、はやぶさが回収した小惑星イトカワの資料を地球に運んだカプセルの展示がなされていた。カプセルを保護するヒートシールドの背面部分は実物展示であり、大気圏突入のすさまじさを感じさせる傷跡が生々しく残っていた。富岡市には、このヒートシールドをはじめ、はやぶさの部品を開発したIHIエアロスペースがある。
 福沢一郎記念美術館に隣接する群馬県立自然史博物館で、はやぶさ帰還カプセル展示の連携講演「宇宙はどうやって誕生したのか~相対論からひも理論へ~」を聴く。国立群馬工業高等専門学校の小林晋平准教授による講演。内容は高度だが、多くの喩えを用いて、たいへん分かりやすく説明されていた。中学校1年と小学校4年の子どもたちも興味深く聴いていた。
福沢一郎記念美術館に隣接する群馬県立自然史博物館で、はやぶさ帰還カプセル展示の連携講演「宇宙はどうやって誕生したのか~相対論からひも理論へ~」を聴く。国立群馬工業高等専門学校の小林晋平准教授による講演。内容は高度だが、多くの喩えを用いて、たいへん分かりやすく説明されていた。中学校1年と小学校4年の子どもたちも興味深く聴いていた。
 自然史博物館では、企画展「脳を学ぶ 脳で学ぶ」が開催されていた。脳の錯覚に関わる多くの展示や、脳の仕組みに関する展示がなされていた。
自然史博物館では、企画展「脳を学ぶ 脳で学ぶ」が開催されていた。脳の錯覚に関わる多くの展示や、脳の仕組みに関する展示がなされていた。
 また、脳の手術に関する映像や、手術室の様子も展示がなされていた。手術着を身にまとい、オペの雰囲気を体験するコーナーもあった。
また、脳の手術に関する映像や、手術室の様子も展示がなされていた。手術着を身にまとい、オペの雰囲気を体験するコーナーもあった。
 群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」が、縦横無尽に活躍している。この企画展でも、脳をひらいたぐんまちゃんが登場した。他のマスコットキャラクターでここまでやるのは、なかなか例がないのでは。
群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」が、縦横無尽に活躍している。この企画展でも、脳をひらいたぐんまちゃんが登場した。他のマスコットキャラクターでここまでやるのは、なかなか例がないのでは。
 自然史博物館のミュージアム・ショップで、長男はアノマロカリス、次男はオウムガイの縫いぐるみを買う。けっこうレアなものがいろいろと売られているショップだ。
自然史博物館のミュージアム・ショップで、長男はアノマロカリス、次男はオウムガイの縫いぐるみを買う。けっこうレアなものがいろいろと売られているショップだ。
 福沢一郎記念美術館では、はやぶさの展示と連携し、メカニック・デザイナーの板橋克己展が開かれていた。板橋克己氏は、宇宙戦艦ヤマト2でデビューし、銀河鉄道999など数多くのSFアニメのメカニック・デザインを手がけた。手書きのイラストは圧巻。
福沢一郎記念美術館では、はやぶさの展示と連携し、メカニック・デザイナーの板橋克己展が開かれていた。板橋克己氏は、宇宙戦艦ヤマト2でデビューし、銀河鉄道999など数多くのSFアニメのメカニック・デザインを手がけた。手書きのイラストは圧巻。
板橋氏ご本人がいらして、自ら作品を語られていた。こちらも質問をし、貴重な経験ができた。子どもたちは熱心に聞いていたので、ごほうびにと特別にオリジナル・イラストのバッジをいただいた。これも貴重なアイテム。自分たちのバッグに大切につけている。
宇宙のマクロから人体のミクロまで、幅広い自然科学の世界から多くの刺激を受けた貴重な一日だった。


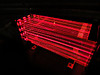






最近のコメント