1985年8月12日- 20年前のこの日、群馬県立万場高等学校で、就職希望者を対象にパソコン講座が開かれた。当時、まだ学校にコンピュータはそれほど普及しておらず、山懐に抱かれた普通科の高校で、生徒ひとりひとりがコンピュータに触れる機会はなかった。そこで、主に事務系を希望する3年生の生徒さんにコンピュータを体験させたいという思いで、企業からパソコンを借りて、6日間の日程で実習を行った。
講座初日のこの日、自作したテキストに沿って生徒が夢中で取り組んでいる姿を見て、いい滑り出しになったことにたいへん気分を良くした。近くの教員宿舎に帰り、お酒を飲んでいると、サイレンの音やヘリコプターの飛ぶ音がやけに響き始めた。当時、教員となって1年目でテレビはおろかラジオすらもっていなかった。
翌日、パソコン講座の会場にいくと、上野村からきている女子生徒さんたちが、昨日はたいへんだったねなどと話していた。「何がたいへんだったの?」と聞くと、「先生知らないの?昨日は飛行機が近くに落ちたので、お父さんたちもみんな山に行ったんだよ。」あわてて新聞を見て、墜落した航空機が524人を乗せていたことを知った。宿直室のテレビをつけると、一面緑の山中にできた傷痕、木々がなぎ倒され茶色い土と焦げた地面が見え、白煙のあがる墜落現場-御巣鷹の尾根が映しだされていた。
この事故を新聞記者の立場で描いた「クライマーズ・ハイ」は、当時の世相や地元の様子を盛り込んでいることもあり、たいへん興味を持って読み進むことができた。
新聞記事をめぐり、社内の確執が大小様々な形で起こる。しかも、新聞には「締切り」という、決断を下す刻限が毎日ある。そのため、独特の緊迫感を持った展開になっている。
群馬県は、県境の半分が屹立した山である。自分にとって、山は身近なものであると同時に、憧れと安心、また時に畏怖の念を抱かせてくれ、乗り越えるべき対象の存在を象徴していた。クライマーズ・ハイは、そんな心象としての山も描かれており、救いのある読後感であった。
クライマーズ・ハイ (文春文庫)


 高崎高島屋の6階展示場で行われた群馬大学主催の「群馬おもしろ科学展」に家族で行く。様々な理科実験を体験できる。子どもたちは、鉱物標本にさわったり、コバルトのあぶり出しをしたり、分子模型を組み立てたりして楽しんでいた。
高崎高島屋の6階展示場で行われた群馬大学主催の「群馬おもしろ科学展」に家族で行く。様々な理科実験を体験できる。子どもたちは、鉱物標本にさわったり、コバルトのあぶり出しをしたり、分子模型を組み立てたりして楽しんでいた。 モーターの工作教室にも参加させてもらった。エナメル線の上半分を紙 ヤスリで削ったものを2枚の磁石ではさみ、消しゴムとクリップの軸受けに置く。コイルを巻いて電池につなぐと、見事に 磁石がまわり、子どもたちも喜んでいた。
モーターの工作教室にも参加させてもらった。エナメル線の上半分を紙 ヤスリで削ったものを2枚の磁石ではさみ、消しゴムとクリップの軸受けに置く。コイルを巻いて電池につなぐと、見事に 磁石がまわり、子どもたちも喜んでいた。
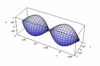


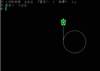


最近のコメント