実社会に活用される数学
銀行の方を講師に招き、「実社会で活用される数学」という題で、高校10年目にあたる数学科の先生に対して講義をしてもらう。昨年度に引き続き、2度目の講義。
「数学は美しいと思いますよね。」
とう言葉で始まり、数学科の先生たちとコミュニケーションをとりながら話が進められた。銀行の実際と金融工学の話題を基に、数式を織り交ぜながらの話だった。
債券利率のイールドカーブの補間関数や、正規分布の確率密度関数など、板書によって説明された点は、特に受講者の関心をひいた。
また、理系の人材が益々求められていることが力説され、数学を教える先生たちの励みになった。
数学を真剣に学ぶ人々を育てることの重要性がじっくり伝わる講義であった。
新学習指導要領では、高校においても数学の意義や重要性を一層重視することが強調される。その点でも、この講義は、これからの数学教育の方向に合致した内容であった。単に美しさを求めるだけでなく、生きた数学を学ぶことの大事さが伝えられ、受講生も刺激を受けたことであろう。
数学が実社会を支えていることを伝えることは、今後も大きな課題。







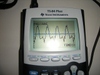






最近のコメント