元旦の朝7時、久しぶりにジョギングをする。6kmほど走る。「一年の計は元旦にあり」を子どもに示すためである。走って家に戻ると、長男が起きていたので、「一年の計は元旦にあり」って知ってるかい。と聞くと、「計って、計画のことだよね。さっきママに聞いたよ」と答える。教えようと思ったこちらとしては、ちょっと面白くない。気をとりなおして、「さて、私の今年の計は…」と、紙に「健康」と書く。我ながら汚い字だ。「パパはね、ジョギングを始めたよ。」で、長男はどうするのかと尋ねると、紙に「たくさん本を読む」と書いた。よしよし。
長男が、「三人寄ればけんかばかり」とか、「能ある鷹は爪をみがく」とか言っている。それ、違うんじゃないと言うと、国語辞典に書いてあったとのこと。そんな間違ったことを書く辞典はケシカランと思ったが、それは、一ヶ月前に自分が買い与えた国語辞典だった。
「逆さに読んでも同じ言葉で、岸なんとかというのがあったんだけど…」と、長男は国語辞典をぱらぱらめくり、「あった!」」と叫ぶ。そこには、「岸にササニシキ」と書いてあった。そんなものは、パパも知ってるぞと、「シナモンパンもレモンパンもなし」とか、「さけをたがいににいがたおけさ」などと書く。冷静に振り返ると、大人げない1年の始まりだ。だいたい、ジョギングが3日と続くとは思えないし、「健康」と一年の計を書いておきながら、現在ワインを飲んだくれている。
さて、国語辞典は、子どもの言葉の世界を広げるのに役立っているようで、いい買い物だったと思っている。学研の「新レインボー小学国語辞典」だ。長男は、ケロロ軍曹の「軍曹」は、どれほど偉いのか、辞書を引き調べていた。階級上は、ケロロ軍曹より、クルル曹長のほうが偉いようだ。また、長男は、辞書に載っていたローマ字の一覧にふりがなをふり、「KERORO」と自分で書いた絵の横に記すなど、活用していた。
この辞典は、引きやすく読みやすい。巻末には、小学校で習う漢字が筆順つきで載っているなど、資料も充実している。下の欄外に、先ほどのことわざパロディや回文、漢字クイズなどが載っており、国語に親しみやすくする工夫がなされている。自らの国の言葉に誇りを持つためには、まず、その言葉を好きになることから入るのがよいだろう。その意味で、この辞典は子どもの言葉の世界を広げるよいきっかけになるようだ。
自分も、言葉をより大事にするために、このブログを続けていきたい。そのために、息切れしないよう、自然体でこの1年も望んでいきたい。
新レインボー小学国語辞典
金田一 春彦 金田一 秀穂




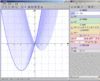
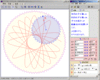






最近のコメント